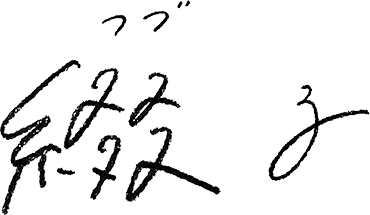雑誌
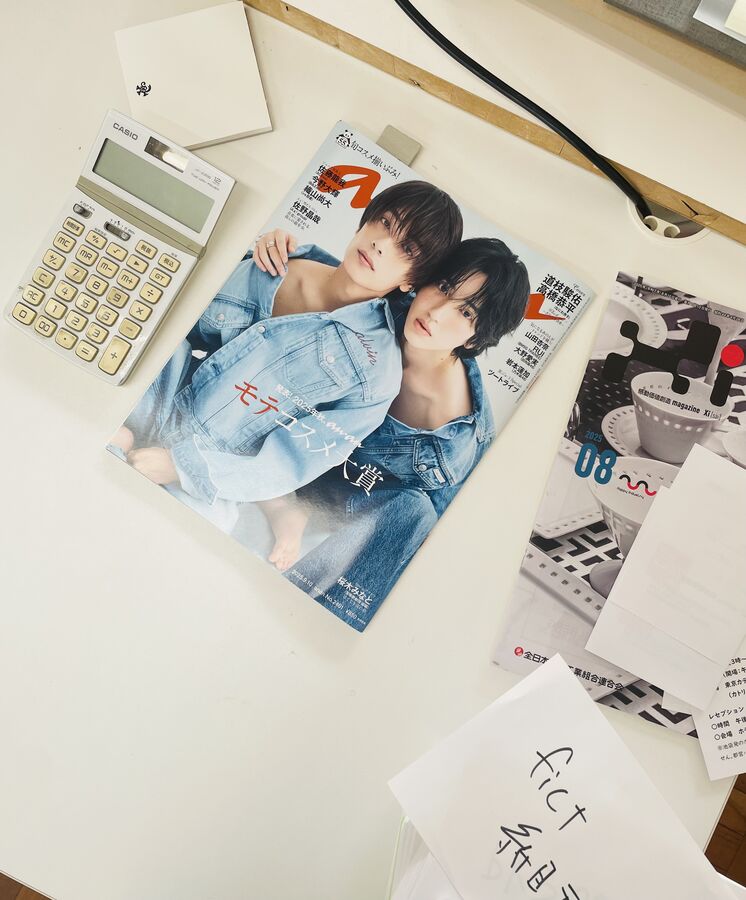
社長 (篠原) のデスクの上に「anan」。
カバーは男性アイドル。流行りの「推し」というやつの一種なのか。
本として珍しいビジュアルが弊社にあるものだからついつい目がいってしまいました。
みなさん、最後に雑誌を買ったのはいつですかね。頻繁に買いますか?
ある大学の先生が「今の若い人は雑誌を読まなくて雑誌エディトリアルや紙媒体の分野を教える立場としてこれからどんな授業を構成していこうかと考えているのですよね…」というお話しを聞かせていただく機会がありました。私は雑誌が豊富な時代に10代20代を過ごし、特にカルチャー誌には大変お世話になっていましたし、今の自分をつくってもらったとも思っています。だから若い人が雑誌に触れないと聞くとちょっとさみしい気持ちにもなりますが。
その先生とのお話から、雑誌にまつわることをぼちぼちと考えてみました。
確かに、instagramをはじめ、情報をより身近にリアルに感じられる媒体はたくさんあるし、もはや紙の雑誌は買わなくとも…正直、思ってしまいます。
ただ、雑誌には編集者やディレクター、ライター、カメラマンがいて情報を発信するプロたちが集まってつくられたもの。1冊にはその誌のスタイルがあって〇〇誌ならこう伝える、みたいなセンスがそこには宿っていると思います。受け身かもしれないけれどそのセンスに素直に浸ってみるというのもいい。そして、〇〇誌を読む・好む人ってこういう感じだよね、というように雑誌でその人の好みを知るという見方もありました。若い頃はそれで親近感が湧いたり、時には友人になれたり。
雑誌のつくり手側が伝えようとしている世界観を読み取る力みたいなものは誌の内容だけでなく、フィジカルな紙媒体を通して自然と無意識に?養われていたのかもしれないと今思い返せば思います。年齢を重ねた今でもかつて読んでいた雑誌のことを思い出そうとする時ってサイズ感だったり、結構ラフな紙を使ってて文章多めの音楽雑誌だったな、写真の見せ方が大胆で好きだった、とか。あのファッション誌は広告が少なくて薄さが好きだったな、とかとか。こうして今書いてみると色々感じとっていたのだなと気づくし、思い出そうとすると案外色々出てくるものですね。あと、カルチャー誌では好きなアーティストのページは隈無くクレジットなどもチェックしていました。そこで好きな写真家を見出したりして、自分の「好き」をじっくり構築していくのが楽しかった記憶が蘇ります。
スマートフォンの小さな画面で次々不特定多数目に入る情報の扱い方とはまた別ものだなと思います。今は情報が身近すぎ&ありすぎて実は記憶に残りにくいかも?とも感じています。手軽すぎでありがたみも薄いような。でも、現代は自分の「好き」を深掘りするにはいくらでも超絶簡単に情報は手に入るし、むしろ今の時代の方が「個」や「好き」目的がはっきりしていればいくらでもそれに磨きをかける環境は整っているよな、とも思います。…トピックがやや広くて取りとめのない話になってしまいましたが。ちなみに私はタブレットで雑誌を読むのが苦手です。すぐに読む気が失せてしまうのですが、なぜでしょうね。

ところで、社長デスクの上にあった「anan」は印刷加工連の商品が紹介されたということでの献本でした。篠原紙工が関わった本やものが雑誌に載ると若い頃にページをワクワクしながらめくっていた時のあの感覚を思い出します。でも、今はその当時とは違って純粋に見る側というのではなく、雑誌を通して(仕事で携わった商品や本が)誰かに「いいな!」と思われてると良いなと思うワクワクですが。