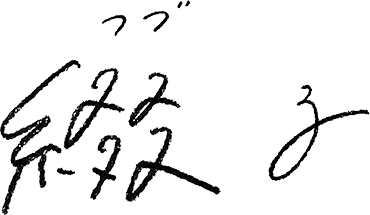隠岐の続き

2023年の頃でしょうか。隠岐島や焼火神社の資料写真を初めてみた時、見たことがない日本という感じで「行ってみたいなぁ…」と思ったのを今でも覚えています。そして今年、篠原紙工図書室で神迎えの展示期間中、私がいちばん作品達と時間と空間を長く一緒に過ごしました。にわかな知識でも図書室に来る方々への作品説明は要所を掴んではお話しすることはできましたが、隠岐島のことは行ったことがない故に想像で話してることろもありました。
しかし、何度も同じことを話していると島や神迎えの本に対して不思議な親近感が湧いてくる気持ちになるのですから言葉には魔力があります。それに加え、図書室の高い天井に浮かぶ水野さんの神楽の絵や谷さんが作った試作物たちから発する隠岐エネルギーが実はじんわりと私の心に染み込んできてたのでしょうか。隠岐にはいつか必ず行ってみようという思いがだんだんと強くなっていったのです。ただ、その時点では「いつか」でしたが。

そんな矢先、もしかしたら、「神迎え」の本を篠原紙工が代わりに海外に紹介する日が来るかもしれないという未来を想像させる出来事がありました。そして、そのちょうど1週間前に、現地で行われる「隠岐だからこそ生まれたアートと本」の展示のご案内が届いていました。このふたつの出来事のタイミングを考え、「行った方がいいのかも?いや、行こう。」と決めたのでした。海外に持っていくことも100%確約ではないのですが、もし、行くことになったとして、自分の言葉で話せる作品と、著者から聞いたことを伝えるのとでは言葉の力が大違いです。しかも異言語での説明ですから母国語のように自由な表現ができるわけではないので自分の中にないものはますます単語・言葉として出てきません。自分の五感を使って焼火神社や隠岐島を感じてくるのが一番だと思いました。

その目的を持って数日でしたが実際に島に滞在し、島の人々に会い、話で聞いていたあの人はこの方で、この方はあの人だ、と頭の中の情報が整理されていくようでした。今回の滞在で、何よりも一番強く感じたのは、魅力的で温かい人たちに支えられて神迎えはできたという本の背景にある人間模様です。本の題材である焼火神社や御神楽、伝統、歴史、物語の美しさ、島の雄大さを感じれたことももちろん重要ポイントではありますが、それらを実際に動いて形にしていくのは人間であり、その現地の躍動感を垣間見れたのが今回の旅の大きな収穫だと感じています。助け合いながら物事を楽しもうとする一人ひとりの高いエネルギーがあってこその本だということが心底理解できました。私たち篠原紙工は製本の段階からの関わりで、それまでの話はじっくり聞かせていただいてはいるのですが、やっぱり、見えないことだらけでした。「百聞は一見にしかず」という言葉以上にこの気持ちの表現が見つかりません。

人が人を紹介し、その紹介から物事が生まれ、それを動かそうとするときに助けてくれる人が現れ、偶然の出来事が起こったり、またそこから予想外な展開が始まり…というように、神迎えは人と人の繋がりと、何かに動かされているような運命的な本。稲垣さんご本人も時々そんな言葉を仰られているのが今ではしっかりと納得です。

製本会社のスタッフが自社が手がけた本の所以の地を訪ねるなんて、そうそう無いかと思います。しかし、振り返れば神迎えは打ち合わせの際もとてもいい空気が流れていて、制作期間も長かったことや柔らかそうな和紙が工場内にあるというのも目を惹いて私個人の中でも社内でも印象深い作品だったことを思い出します。その当時は私が行くと決めるなんて全くもって想像もしていませんでしたから、これこそやはり何かに動かされているのかもしれません。

製本会社はどのお客さんにとっても、本をつくると決めてから登場するビジネスパートナーですが、神迎えだけに限らず、篠原紙工にきてくださるお客さんの本の背景にはいつも私たちが見えない、分かりきれないストーリーがそこにはあるのだろうと思いました。私たちはその見えない部分を想像しながら手を動かすということも大切な仕事の心です。本とは、紙に印刷されたものを束ねて綴じた物という単純な意味合いだけではありません。著者や関わった方々のこれまでのストーリーや想い、物語、言葉など本の内容、それらの魂を宿わせる器が本であり、その大切な魂に見合ったものを考えて提案することが篠原紙工の仕事です。今回の旅ではそのことがますますと実感でき、改めてこのプロジェクトに携われたことを嬉しく思います。先に書いた海外に神迎えをご紹介できる現実は確実になるのか…まだ未知ではありますが、現実になることを想像して静かに準備をしようと思います。